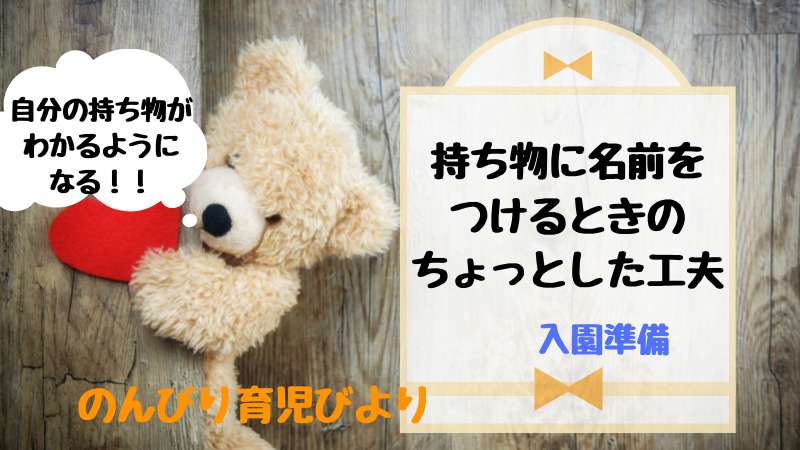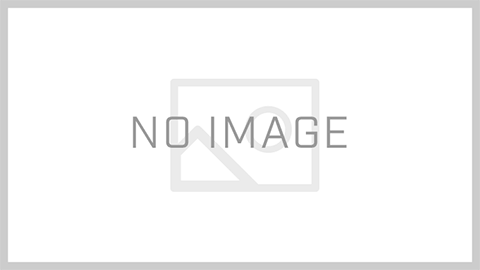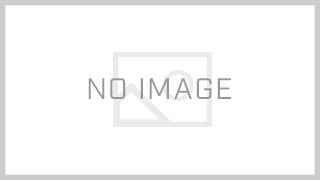元保育士で3児のママ、ゆかりです。
入園前の準備として、やらなければならないのが名前書き。
これが...なかなか大変ですよね。
“入園準備のほとんどが名前書き”といっても、過言ではありません。
名前がないと、持ち物が迷子になってしまいます。
なので、下着やクレヨン1本など...
どんなに小さな物にも、必ず名前をつけておく必要があります。
- 子どもが安心した園生活を過ごせるように
- 持ち物が迷子になってしまわないように
持ち物に名前をつけることはとても大切。
でも実際に名前を書こうとして...
- どんなことに気をつければいいの?
- 字が読めない子どもが、自分のものとわかるにはどうしたらいいの?
と悩んだことありませんか???
- 名前をつけても、子どもの持ち物が迷子になっちゃう...
- 子どもが、友達の持ち物と自分の持ち物を間違えてしまう...
そんな経験はありませんか???
ほんの少し気をつけるだけで、【持ち物の迷子問題】も解消されると思います。
それでは、名前つけのポイントなどをお話していきますね。
名前をつけるときのポイント
名前をつけるときのポイントは2つです。
- わかりやすいこと
- ものによって、記名方法を使い分けること
順にお話しますね。
①わかりやすく
様々な方法がありますが、1番重要なのは〈名前がしっかり見えること〉です。
見えづらいとせっかく名前をつけていても意味がありません。
色が濃いものの場合は、直接書くよりもお名前シールや布テープなどに書いた方が見えやすくなります。
*ただし、それは園の中で使うものに限ってのこと。
外出時にすぐ名前が見えてしまうのは、このご時世、防犯上よくありません。
靴や帽子など、通園時に身に付けるものは目立たないところ(内側など)につけた方が、個人的にはいいと思います。(園によっては指定されるかもしれませんが...)
私がオススメしたい【靴にお名前をつける方法】をご紹介♪
②ものによって、記名方法を使い分ける
名前をつける方法はいくつかありますね。
- マジックで書く
- お名前シールなどをはる
- お名前スタンプを押す
それぞれにメリット、デメリットがあります。
そして、物によっては向き、不向きもあります。
“何を使うのが正解”ということはないので、必要に応じて組み合わせるといいかもしれません。
用品ごとに使い分けることで、書いてある名前がわかりやすくなると思います。
私も用品ごとに
- 布テープ(ゼッケン)→巾着などの布用品
- マスキングテープ→洋服(タグ)
- 名前シール→洋服(タグ用)&コップなどのプラスチック用品&水筒など
- 名前スタンプ→靴下&ゼッケンに押して布用品に...
など、使い分けています。
ネームリボンやネームタグなどを使うこともあります。
【小さい子でも、自分の持ち物がわかる】名前の書き方
<わかりやすく、はっきりと>を心がけていても、ひらがなが読めない年齢だと自分の持ち物がわからないことも多いです。
そこで、<ひらがなの読めないお子さんでも自分のものとわかるようになる>名前の書き方(ポイント)をご紹介したいと思います。
名前の横にマークをつけよう
保育園や幼稚園ではロッカーなどの至るところに、個人のマークがついているのをご存じですか?
ひらがなが読めない年齢の子どもでは、なかなか名前を認識できないですよね。
長く使っていくうちに【自分の場所はここ】とわかってきますが、時間がかかりますし、時々間違えてしまうこともあります。
そこで使っているのが個人のマーク。
このマークがあるだけで、小さい子でもここが自分の場所、これが自分のもの、とわかり、安心するのです。
この方法、全ての記名方法に応用できます。(スタンプは物によります)
自分で描くもよし、お名前シールをお店で頼むのなら、注文時にマークをつけるもよしです。
1番わかりやすいのは園のマークと同じマークをつけることですが、入園前の説明会などの段階では決まっていないことも多いと思いますし、なかなか聞きづらかったりもしますよね。
入園準備をする時に”わかったらラッキー”くらいに考え、好きなマークを決めてしまってもいいと思います。
そのときは、子どもが好きそうなものを選んであげるといいです。
子どもに「何がいい?」と聞いて、一緒に決めるのもいいでしょう。
持ち物全てに同じマークがついていれば、ひらがなの読めない子もマークを見て自分のものとわかりますね。
持ち物全部に対応できます!!
色帽子やスモックなどにも、〈ワンポイントとして好きなワッペンをつける〉ことで、ぐんと間違えにくくなります♪
マークがつけられるお名前シールは、こちらを参考にしてみてくださいね♪
★楽天でチェックするなら...
★Amazonでチェックするなら...
好きなキャラクターがあるなら、キャラクターのネームシールなどもおススメ
キャラクターの可愛いネームシールやネームラベル、ネームワッペンなどもありますよね。
こちらで統一するのもわかりやすいです。
*キャラクターものが禁止の園もあるそうです。
準備するときは、お気をつけください。
好きなキャラクターだと覚えやすいですよね♪
統一することで”自分のもの”とわかりやすくなります。
キャラクターのものは少しお高めな印象です。
持ち物すべてに...となるとかなりの数になってしまうと思うので、費用は少しですが割高になってしまうかも。
ただ、キャラクターのネームシールやネームラベルなどはしっかりとしたものが多いので、名前も見やすくキレイです♪
アンパンマンが好きな子に、アンパンマンで揃えることもできますね。
統一できなければ、いくつかのマークがあってもいい
すべての持ち物に同じマークをつけて記名する
- 園のマーク
- 名前シールのマーク
- 手書きのマーク
- 園のマークが入園前にわからない
- 園のマークと同じマークの名前シールがない
- 名前シールを使えない用品(持ち物)もある
- 園のマークが手書きするには難しい
などなど...
全部、同じものに統一できれば、〈わかりやすこと間違いなし〉なのですが...難しい理由もあります(泣)
そんな時は、1つのマークにこだわらず、いくつかのマークを使ってみてください!
- 園のマーク
- ご自分で選んだマーク①
- 園のマーク
- ご自分で選んだマーク①
- ご自分で選んだマーク②
- 園のマーク(手書き)のみ
- 園のマーク(スタンプ&手書き)
- 自分で選んだマーク①(名前シール)
(長女のときは園のマークで全部統一していました。)下二人は、名前シールの便利さに目覚め...
洋服用シール(タグ用)、その他の名前シールの絵柄を揃えて使っていました。
布用品、スモック、体操服などは手書きやスタンプで園と同じマークをつけていました!
(我が家は、さかなとペンギン♪)
マークをいくつか組み合わせるときの注意点は、種類が多くなりすぎないこと!
- 覚えられない
- わかりにくい
全ての持ち物に名前をつけよう
保育園や幼稚園などで集団生活を送るにあたって、この記名はとても大切です。
お家とは違い、先生たちが園児の個人の持ち物を全て把握することはできません。
また、全く同じものを持っている場合もあります。
”すべての持ち物にはお名前を”が集団生活でのルールです。
時間をかけてつけた名前。
せっかくつけたのだから、”子どもが自分のもの”とすぐにわかるようになった方がいいですよね。
個人マークは、保育園でも幼稚園でも取り入れている方法です。
製作物などにもマーク貼ったりしているくらい、たくさん活用しているんですよ。
ご家庭で注文した【マークつきお名前シール】を使っている子も多いのですが...
マークつきのお名前シールを持っていても、すべての持ち物にお名前シールを使っているわけではない...というパターンが多いんですよね。
《お名前シールをつけていない持ち物(手書きなど)には、マークがない》ということが多いので残念だな~と思っていました。
せっかくマークがあるのなら、ぜひ、全ての持ち物につけてあげてくださいね。
全部同じマークじゃなくても、お子さんがわかっていれば大丈夫です!
(目安は2〜3こ)
少しでも参考になれば、嬉しいです。
『靴のお名前はどうやってつけようかな?』と思ったら、ぜひ読んでみてくださいね!↓↓