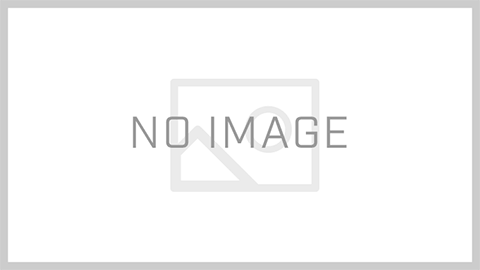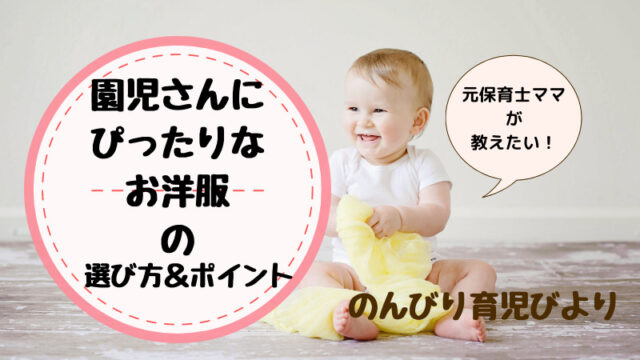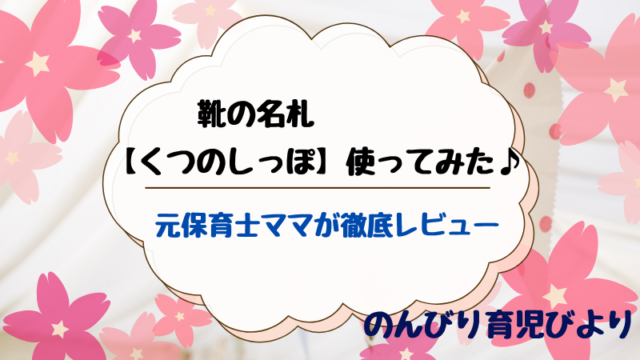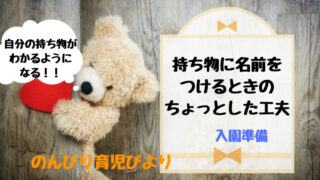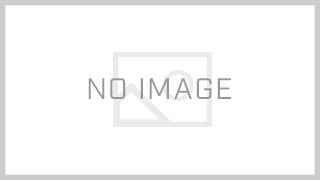元保育士で、3児ママのゆかりです。
お昼寝布団は、【保育園生活になくてはならない、大切なもの】ですが...
いざ準備をしようと思っても、どんなものを選んだらいいのかわからなかったりしますよね。
入園面接などで持ち物の説明をしていたときに、
保護者の方から質問が多かったのが”お昼寝布団について”でした。
私自身も、入園準備の中で1番悩んだのが、お昼寝布団かもしれません。
特に大きな買い物になりますから、失敗はしたくないはず。
この記事では、そんな悩める保育園のお昼寝布団について、
- 選ぶ時のポイント
- 注意点
などを保育士目線でお話したいと思います。
保育園によっては”お昼寝用のお布団→業者さんでリースしている”というところもあります。
ご購入する前に、必ず園の方にご確認くださいね。
保育園のお昼寝布団ってどんなものがいいの?
早速ですが、保育園のお昼寝布団は、どんなものがいいと思いますか?
やはり1番は、寝心地のよさ?
たしかに、子どもにとっても、寝心地はいいに越したことはないですよね。
気持ちよく眠れた方が、いいに決まっています。
ただ、”寝心地がいい”だけでは決めないでほしいです。
お昼寝布団を選ぶときには、大切にしたいポイント(注意点など)があります。
お昼寝布団を選ぶときに注意したいこと
保育園のお昼寝布団を選ぶときに、注意したいことがあります。
それは
- 布団の固さ
- 布団の重さ
- 大きさや収納方法
です。
順番にお話していきますね。
①布団の固さ
一般的に”布団といえば柔らかい方が気持ちがいい”と思いがちですが、乳幼児の布団はあまり柔かすぎないものがいいです。
特に赤ちゃんの場合は...
柔らかすぎると、たとえば寝返りなどをした際に布団が沈みこみすぎて、顔などが埋まってしまい呼吸を妨げる恐れがあるんです...
もちろん保育園では、
- できるだけ、うつ伏せ寝はさせないようにする、
- 寝入りがうつ伏せでも、仰向けに変えたりする
などと対応はしています。
そして必ず保育士が側で見守って、子どもに変わったことがないか、よく注意しています。
保育園のお昼寝布団では、柔らかい布団(体が沈んでしまう布団)は選ばないようにしてくださいね。
②布団の重さ
保育園のお昼寝布団は、あまり重すぎないものがいいです。
なぜなら...
布団の持ち帰りがあるからです。
持ち帰りの頻度は園によって異なりますが、
多いところでは、毎週末に持ち帰る必要があります。
③大きさや収納方法
園によっては【収納や、実際に布団を敷くスペース等に限りがある】ため、大きさを指定してくる場合があります。
よく確認してくださいね。
ちなみに、一般的なお昼寝布団のサイズは70×120です!
もしかしたら...
“ベビーベッドで使っていた布団(マットレス)を、現在使っていないから保育園で使いたい”と考えている方もいるかもしれません。
たしかに持っているお布団を活用できたら、いろいろと助かりますよね。
でも、マットレスタイプはやめておきましょう。
マットレスタイプの布団は、
- たたむことができなかったり、
- たたんだときに厚みがありすぎてしまって園側でも困る
ということがあります。
【たたまずに、園児全員の布団を収納することができる園】なんて、ほとんどありませんし、布団の持ち帰りの際にも大変です。
ミニサイズのマットレスも同様です。
そして、小さいとすぐに使えなくなってしまいます。
子どもは成長するものです。
あまり小さすぎると、卒園までにサイズが合わなくなってしまいます。
*布団を【くるくる丸めて収納する園】もあるようです。
必ず、園の方にご確認くださいね。
折りたたみできる布団でも、たたみ方にも気をつけて
布団のたたみ方(折り方)も、二つ折りと三つ折りがあるので気をつけてくださいね。
そこまで細かく指定されない場合もありますが、心配ならば確認した方がいいと思います。
保育士時代にオススメしていたお昼寝布団
布団にもいろいろと種類があると思いますが、
私が保護者の方におすすめしていたのは、固綿布団です。
収納方法がくるくる丸めるという園では、固綿布団は使えないと思うのでご注意ください。
固綿布団のいいところ
固綿布団のいいところは
- 程よいクッション性がある
- 体が沈みすぎず、反発もある
つまり...
子どもの体が、布団に沈みこんでしまうことがありません。
子どもが使うのに安心ですね。
さらに寝心地も、そんなに悪くないです。
固綿布団は若干の厚みがあるので、冷えにくいのもオススメポイントです♪
固綿布団のデメリット
固綿布団はしっかりしている分、重たいものも多いです。
また厚みがある分、かさばります。
私が働いていた園では、幼児クラスになると、布団を自分で片付けたりします。
そのとき、布団がしっかりしすぎてしまう(重たすぎる)と、子ども達はやりにくそうにしています。
もちろん保育士が手伝ったりしますが、友達が一人でやっていると”一人でやりたい”という子もいるので、必死になっている子どもの姿に少し切なくなります。
また持ち帰りの時も、重たいと大変ですよね。
車で送迎している方はいいですが、徒歩、自転車等ではかなり大変だと思います。
オススメの固綿布団
固綿布団にも種類があり、比較的厚みが少ないものもあります。
厚みが少ないと、その分お布団も軽くなり、デメリットが少しカバーできます。
お布団の厚さ(高さ)と重さに注意すれば、デメリットはあまり感じなくなるかもしれませんね。
保育園のお昼寝布団なら、
布団の厚さは”3cmくらい”がちょうどいいと思います!
★オススメの固綿布団は、こんな感じです★
オススメその①〈布団の厚さ2.5cm〉
オススメその②〈布団の厚さ3cm〉
お昼寝布団は、セットで買った方がいいの?
お昼寝布団セットというものもありますよね。
- 敷き布団
- 掛ふとん
- シーツ
などがセットになっているものです。
娘入園当時は、【固綿布団のお昼寝布団セット】ってあまり見かけなかったのですが...
最近は固綿布団のものが増えている印象です!
お昼寝布団セットについても、少しお話しますね。
お布団セットのいいところ
お布団セットは、シーツやかけ布団などが一式そろっているので、
例えばシーツのサイズなどがあっているかetc...心配する必要はありません。
そしてシーツ、掛け布団カバーなどの柄が統一されている場合が多いので、お子さんも自分のものと認識しやすいです。
お昼寝布団セットの固綿布団は、お布団自体も比較的軽いので、
- 大きくなってくればお子さんでも持てます。
- お子さん自身で布団の片付けがしやすいです。
おすすめしたい<固綿布団のお昼寝布団セット>を2つご紹介しますね!
オススメその①
オススメその②
どちらのセットも全部お洗濯できるのようなので、本当におすすめです!
持ち運び用の袋までついているので、便利すぎますね♪
セット購入のデメリット
セット購入のデメリットは、
- デザインや色などを細かく選べないこと。
- 使わないものがセット内容にあるかもしれないこと。
だと思います。
①デザインや色などを細かく選べないこと
セット商品は、シーツの柄や色などの組み合わせはすでに決まっています。
セットによっては、デザインの種類はいくつかあります。
が、組み合わせを変えることはできません。
- こだわりたい柄
- 好きな色
などがある場合は、《セットではなく、それぞれを単品購入する》ことをおすすめします。
②使わないものがセット内容にあるかもしれないこと
便利なお昼寝布団セットですが、《保育園で実際に使わないもの》がセットに入っている場合もあります。
たとえばですが、
まくらは使っていない、という園は多いです。
また、掛ふとんではなく、タオルケットやベビー毛布を使っているという場合もあります。
これらについては、園によります。
実際に通われる園に、お昼寝で必要なものをご確認くださいね。
【セット内容】と【実際に必要なもの】は、しっかりと確認しておくと安心です!
ただ、《保育園では使わないけど、お家で使う》ということもできますので、大きなデメリットにはならないと思います。
セット購入をするときに気をつけたいこと
お昼寝布団セットを購入するときには、以下のことに気をつけるといいです。
- 園で必要なものを把握しておく
- セット内容を確認する
- お布団の素材などをしっかり確認する
- 固綿布団のものを選ぶ
そして、<お布団セットには含まれていないけど、必要なもの>を追加購入することを忘れないでください。
たとえば
- 防水シーツ(敷きパッド)
- 洗い替えのシーツ
- タオルケット
などです。
- お布団セットを購入するときに、同じショップでまとめて購入もOK♪
- 単品購入ができるショップなどで、サイズ確認をした上で追加購入もOK♪
私の経験上、シーツや敷きパッドは洗い替えがあったほうがいいです!
お仕事復帰になると、一気に忙しくなってなかなか時間も取れなくなります。
<私がお昼寝布団以外に購入したもの>についても詳しくお話しています↓↓
入園準備〜元保育士の体験談!我が子のお昼寝布団と一緒に用意したものをお話します〜
また私は、固綿布団を強くすすめてはいますが...
通園方法などで”とにかく運びやすさ重視”という方は、<固綿布団じゃないお布団セット>がいい場合もあるとは思います。
ぺちゃんこになってしまったら、布団だけ買い替えもできますしね♪
メーカーは変わってしまうかもしれませんが、お布団の単品購入もできます。
何を重視するかによって、布団を選ぶポイントは変わってくると思います。
それぞれの条件にあったものを選んであげてくださいね。
オススメのお布団セットはこちら♪
保育園での収納方法が”布団をくるくる丸めるという園”は〈比較的薄めで固綿布団ではないもの〉がいいのかと思われます...(断定できず...すみません)
私が我が子に購入したお昼寝布団
固綿布団とお布団セットについてご紹介してきました。
ここからは実際に私が保育士として現役で働いていたころに、我が子に購入したお昼寝布団のお話をしたいと思います。
長女が入園したのは1歳になる月でした。
まだまだ赤ちゃんと言われる年齢。
”固綿布団がいい”と思う反面、重たいのはやはりネックです。
でも、あまり薄いものは買いたくないというのが本音...
当時、私なりに検討を重ねました。
そして、購入したのが西松屋オリジナルの固綿敷布団でした。
こちらのお布団は、程よい厚み(3cm)でお値段もお手頃価格。
シーツ等、追加で購入しなければならないので、実際の費用はもう少しかかりますが、お財布に優しい価格設定でした。
布団そのものはスポンジのような素材なので洗えませんが、カバーがついていてそちらを洗うことができるので清潔に使用できます。
使い続けていくうちにぺちゃんこになってしまっても、「このお値段なら、最悪買いかえてもいいかなー」と思ったのも購入した理由です。
またシーツや掛け布団など、自分の好みを組み合わせられるので、別売りの方が個人的には満足でした。
お昼寝布団以外に購入したものについて、くわしくはこちらをご覧ください♪
程よい厚みと程よい軽さは、現場の保育士さんにも好評でした♪
実際に入園前の面接などでも、うちの子の布団を見本として見せていたようです。
〈似たようなタイプの固綿布団〉をチェックしたい方はこちらからどうぞ↓↓
オススメ固綿布団 その①〈布団の厚さ2.5cm〉
オススメ固綿布団 その②〈布団の厚さ3cm〉
敷布団&布団カバーの2点セットもあります♪
という方にオススメです♪
当時はネットで購入するという考えがなくて店頭で買ったのですが、再購入するならネットにするかな~と思います。
西松屋さんの楽天ショップは、
<3,980円以上で送料無料(離島・一部地域を除く)>となっているので、一緒に敷布団カバー(シーツ)や敷きパッド(防水シーツ)を買うといいですよ〜♪
★私がお布団と一緒に購入した敷布団カバー(シーツ)と同じタイプの敷布団カバーはこちら♪
〈厚み2〜3cmまでの布団用〉
〈厚み5〜6cmまでの布団用〉
★私がお布団と一緒に購入した敷パット(防水シーツ)と同じタイプの敷パットはこちら♪
さいごに
保育園のお昼寝布団について、お話させていただきました!
私がおすすめしたいのは、固綿タイプのお昼寝布団。
購入するなら
- 厚さが3cm程度の固綿布団
気に入ったものがあれば
- 【固綿布団のお布団セット】
が、とっても便利でオススメー!!
でも結局のところは、【保育園やご家庭の条件にあった布団】を購入することが1番です。
重視するポイントがどこかによって、選ぶ布団も変わってくると思います。
園にもよりますが、0歳児から入園して長ければ6年間も使用するものです。
後悔のないよう、選びたいですよね。
保育時間の中で子どもの体を休める、大切なお昼寝の時間。
元気いっぱいの園生活を過ごすためにも、お昼寝の時間は子どもにとっては本当に大切な大切な時間です。
そして成長に欠かせない、大切な時間でもあります。
ぜひ、参考にしてみてくださいね。