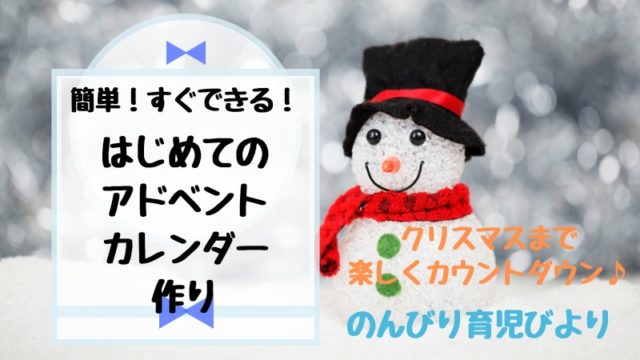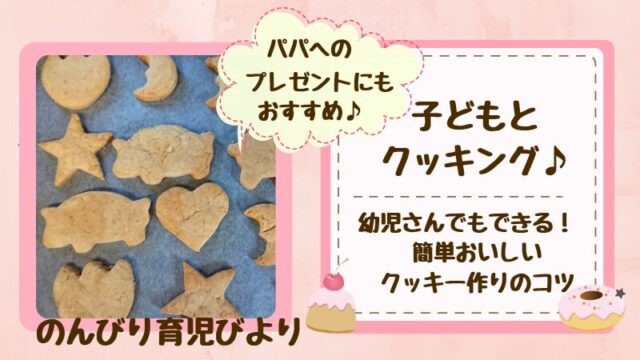元保育士で3児のママ、ゆかりです!
2月3日は節分ですね。
子どもにとっては、ドキドキ(ちょっと怖い?)しちゃうイベントの1つ...
0、1、2歳くらいの小さなお子さんにとっては、まだ参加しづらかったりしませんか?
節分とは言えば、やっぱりメインは鬼と豆まき。
子どもが小さいと鬼は怖がっちゃうし、豆はまだ食べられないし...
と、楽しむにもハードルが高いですよね。
そんなときは、【大人が主体になって、一緒に雰囲気を味わう!】でもいいと思います。
鬼が怖くて泣いてしまうのも、【小さい時期だからこそ、の思い出】になりますよね。
とは、言っても...
- 泣かせてしまうのは、何だか可哀想で
- 小さい子なりに、節分気分を味わえないかな?
という方もいると思います。
言うことはないですよね。
実際に保育園では(特に0.1.2歳児クラスでは)...
- 節分という行事をあそびに取り入れ、
- 無理なく、行事に参加できるように...
という工夫をしているんですよ♪
その① 絵本を読んで、鬼に触れてみよう♪
まずは、絵本を読んで鬼に触れてみましょう♪
鬼を題材にした絵本は、たくさんあります。
といっても...怖い鬼ではありません!
”鬼=怖いもの”と思いがちですが、可愛い鬼のお話も、実はあるんですよ。
可愛い鬼のお話なら小さい子も楽しんで見ることができます♪
鬼に興味を持つチャンスですね。
オススメの絵本
小さい子でも楽しめる、オススメの絵本をご紹介します。
私がオススメしたい絵本は次の5冊です♪
*うち3冊はシリーズものです。
オススメ絵本①〜③ ★おにの子あかたろうシリーズ
赤鬼のあかたろうくんのお話です。
↑↑こちらは3冊セットです。
鬼のシンボルであるつのに困ったり、お友達のおにの子たちとの色の違いを不思議に思ったり...
とってもほのぼのした、可愛いお話です。
とっても可愛い鬼たちなので、<鬼=怖い>のイメージはなくなると思います♪
1冊(単品)でも購入できます!
★あかたろうの1・2・3の3・4・5のご購入はこちらから↓↓
★へえー すごいんだねのご購入はこちらから↓↓
★つのはなんにもならないかのご購入はこちらから↓↓
オススメ絵本④ ★おにのパンツ
【おにのパンツ】の手遊びはご存知ですか?
保育園や幼稚園ではよく歌われている、子どもに人気の手遊びです♪
手遊びの歌詞がそのままで、絵本になっています。
手遊びをモチーフにした絵本なので、一緒に歌ってもとっても楽しいですよー!
オススメ絵本⑤ ★ももたろう
こちらは可愛い鬼ではありませんが、鬼退治=豆まきを連想させやすいです。
節分当日は<ももたろうのハチマキをつけて、鬼退治(豆まき)をする>のも楽しいですよ〜
ただ、出てくる鬼は普通の鬼(怖いイメージの鬼)なので、”できるだけ、やわらかい印象の絵が描かれているもの”を選ぶといいと思います。
怖さが、少しはやわらぐと思われます。
いもとようこさんのももたろうは、可愛らしい絵なのでオススメです♪
絵本の世界観を楽しもう
絵本を読んだあとは、絵本の世界観を思いっきり楽しんでください♪
- あかたろうくんのお話では、あかたろうくん達になりきって冒険ごっこがオススメです!
- ももたろうでは、ももたろうになりきって鬼退治をしましょう!
可愛い鬼のお面を作って、鬼になりきってあそぶことで、怖いイメージ<楽しいイメージとなります。
また、鬼のお面や的を作って、新聞紙などで作った豆を投げてあそんでも楽しいです。
その② 鬼のお面をつくろう(なりきりあそびをしよう)♪
絵本を読んで鬼に興味を持ったら...
絵本のあかたろうくんのような<可愛い鬼のお面>を作ってみましょう。
喜んでおにの子になりきると思います。
かわいい鬼のお面を作ってみよう
それでは、【かわいい鬼のお面】の作り方をご紹介します。
とっても簡単につくれますよ〜
<用意するもの>
- 画用紙① 鬼の色(好きな色)
- 画用紙② 髪の毛の色(黒や茶色など)
- 画用紙③ つの用(黄色など)
- 画用紙④ 目の色(黒など)
- 画用紙⑤ 口の色(赤やオレンジなど)
- はさみ
- のり(スティックのりがオススメ)
かわいい鬼のお面の作り方
作り方は以下の通りです♪
①〜④までは下準備です。
⑤〜が子どもが作る手順になります。
①色画用紙に顔の形を描く

②画用紙をハサミで切る
③髪の毛色の画用紙を細長く切る

④顔の大きさに合わせて目などのパーツ、つのを作る。

顔パーツは、ラベルシールなどを使うとより便利です♪
赤い丸シールを半分に切ると、口になります♪
あかおにを作るときは、口が赤いシールだと同じ色で目立たないので、
オレンジやピンクなどのシールを使うことをオススメします!
ここまでが準備になります。
ここからは先は子どもが作る手順です。
⑤髪の毛を貼る。(隙間が開いていても、可愛いです♪)
*下に敷いている白い紙は、のりがテーブルにつかないためのものです。

⑥顔パーツを貼りつけていく。

⑦最後に、つのをつける。

頭の大きさに合わせて画用紙と輪ゴムで帯を作り、ホチキス等でつければ、可愛いお面の出来上がりです。
ホチキスは芯の部分が危ないので、頭に触れる面が芯の平らな方になるようにして、さらにセロテープなどを上から貼って保護してくださいね。
心配な場合は、すぐに取れてしまいますが両面テープなどでつけてもいいと思います。
遊ばないときは、お部屋に飾っておいても可愛いです。

その③ 豆まきごっこを楽しもう♪
節分といえば、やっぱり豆まき。
大きな豆を作ろう
新聞紙やガムテープなどを丸めて、豆を作って投げて遊んでみませんか?!

実際に「豆まきをしよう!」といっても...
- どんなことをするのか
- どうやってやるのか
子どもにとっては、わからなかったりします。
豆まきごっこをする
↓
実際に経験する
↓
豆まきがどんなものか、わかるようになる
ということです。
そして節分の当日も、ぜひ手作りの大きな豆で豆まきをしてください。
『食べちゃダメ!!』と声をかけるのも、かけられるのも、意外とストレスがかかるもの。
だったらお互いストレスフリーの大きな豆で、豆まきをしましょう。
手作りの大きな豆も、口に入れるとガムテープなどを噛みちぎってしまうこともあるので、ご注意ください。
しっかりと見守ってあげてくださいね。
大きな豆を入れる<豆入れ>を用意しよう
大きな豆が入る、豆入れも用意してみましょう♪
豆入れはご自宅にある入れ物を使っても、廃材などで作ってもどちらでもいいです♪
小さなバケツは取っ手もついているので、小さい子には使いやすいですよ〜
簡単!廃材を使った豆入れの作り方→準備中です。
大きな豆を使って、いっぱいあそぼう♪
豆まきをする準備ができてきましたね!
- 大きな豆
- 豆入れ
これらが用意できたら、たくさん使ってあそびましょう♪
大人が鬼になって豆まきをしてもいいし、的にむかって投げてもいいです。
また、最初のほうでお話した、<ももたろうごっこ>も楽しめますね。
節分の日だけでなく、ぜひぜひ1月の中旬頃から何気なく遊びに取り入れて、豆を投げてみてください。
小さい子にとっては、【行事前から慣れ親しむこと】が、【当日を楽しく過ごすためのポイント】となります。
ゲームにして遊んでも楽しいです♪
その④ 鬼を作って、盛り上がろう♪
豆まきごっこや当日の豆まきで、大人がお面などをつけて鬼に変身しても、もちろん構いません。
ただその場に大人が1人しかいないと...
必然的にその大人が鬼になるため、子どもは鬼と2人きりになりますよね。
鬼がママやパパなどの身近な大人とはいえ、不安になる子もいると思います。
大がかりに作る必要はありません。
- (何度かお話していますが)お面を壁などに貼ったり吊るしたりして、それを的にしてもいいです。
- 紙に描いた鬼の絵を(こちらはできれば全身を描いてくださいね。)空き箱や段ボールに貼ってもいいです。
- ペットボトルや牛乳パックを使って作ってもいいですね。
大きくなくても、いいんです。
リアル過ぎなくても、いいんです。
「鬼さんがいるよ〜」
その一言で子どもにとっては、鬼に見えることでしょう。
大人も一緒に、創造力を膨らませることが大切です♪
慣れてきたら...
例えば、箱などを動かしたり、「助けて〜」などと言って、逃げる真似をしてみてください。
その⑥ ”年の数だけ豆を食べる風習”はどうする?
豆まきをしたら、【豆を年の数+1つ食べる】のが風習としてありますよね。
0歳はもちろんのこと、1、2歳も小さな豆を食べるのは、誤飲や窒息の可能性があり危険です。
そんな時、保育園で食べていたのが卵ボーロでした。
色も形も、何となく似てますからね。
折り紙で折ったおさんぼうの中に、お弁当用のおかずカップを敷いてボーロを入れれば、気分は節分の豆です。
いつも食べるボーロとは違い、特別感を味わえるでしょう。
上に兄姉がいると...
同じものを欲しがってしまって、赤ちゃん用のものを食べなかったりすることがありませんか?
我が家の次女も0〜2歳当時はそうでしたし、現在2歳の末っ子長男もそうです...
そしてだんだんと、ごまかしがきかなくなってきます。
ねーね(達)と同じものが欲しいようです。
(おいしそうに見えますもんねー!)
おさんぼうに入っていれば、中身は見えにくいし、意外とバレません(笑)
ちなみに保育園の子達も、そばで大きい子が豆を食べていましたが、気にせず自分のボーロを食べていました。(中身の違いに、気づいていないと思います!)
もし、それでもバレてしまったら...(笑)
上の子も一緒に食べるときはボーロにして、後でこっそり豆をあげるといいかもしれません。
〈我が家の場合...〉
次女にはバレず!!でしたが、まさかの長女が卵ボーロを欲しがり...
一緒に卵ボーロを食べました(笑)
そして、月日が経ち。。。
末っ子にボーロ、姉さん達には豆をあげたら...
やっぱり、ボーロをうらやましがる姉さん達(笑)
最後に
<0、1、2歳児の節分の楽しみ方>を、実際に保育園で実践してきたことや、我が子の様子などを元にお話しました。
- 楽しくが基本!
- あそびながら節分の雰囲気を味わおう!
この2点が大事だと思います。
小さい子も小さいなりに行事に触れ、経験することで、刺激を受けたくさん学んでいきます。
【行事に興味を持つことが、小さい子どもにとって1番】だと思いますので、そのきっかけ作りになれば嬉しく思います。
ぜひ、親子で楽しんでみてくださいね。
節分当日は、元気いっぱい豆まきができますように...